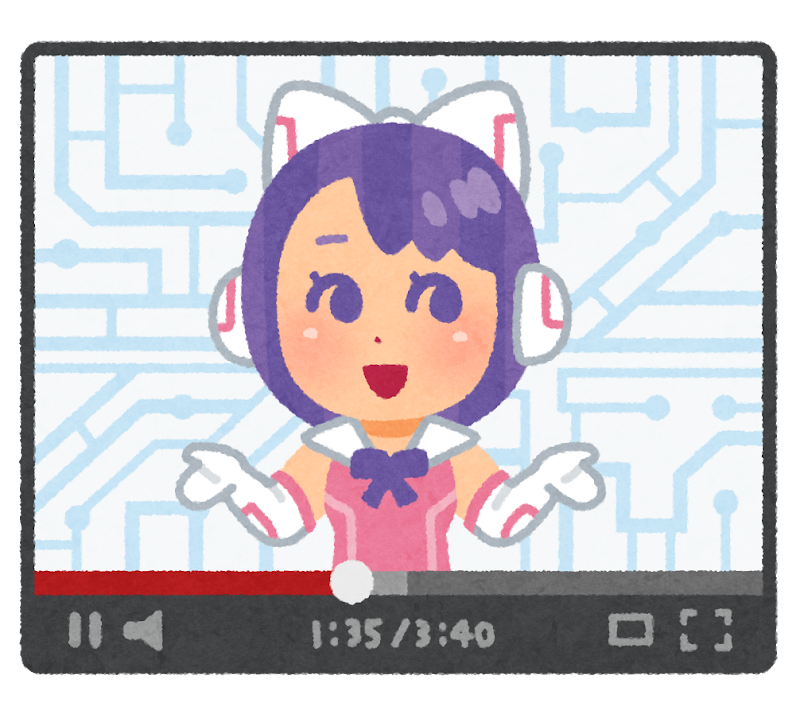まぁこんな修理は、街や電器店やメーカーの修理屋さんでもないかぎり滅多にやることはないので、あくまで備忘録という事で。
この記事には、自前で修理した内容が記載されています。この記事を参考にして修理する場合は、部品が調達できない等の苦情や問い合わせなどの応対はしません。
また修理中の感電事故、更なる故障の発生など、当方では一切責任を負えません。必ず自己責任でお願いします。
自分で修理する自信のない方や、自己責任を負えない方、おカネのある方は、新しい洗濯機を購入することを強くお勧めします。
事の発端(故障状況)
ある日、カミさんから「洗濯機を止めても、水滴が落ちている」と言われたので、確認。たしかに1分弱の間に小さな水滴が数回落ちている。
念のため洗濯層に落ちた水を拭き取り、1時間ほど経過してからもう一度確認してみたところ、やはり水滴が落ちてきていたので、おそらく漏水故障と判断。
故障箇所をネットで調べてみる。
文明の利器ではあるが、洗濯機の水回りの故障というと、洗濯機の側ではなく、とにかく給水栓(要するに水道の蛇口側)のトラブルばかりがヒットしてしまう。
おそらく、そちら側の故障(というか、開栓忘れ)が多いことが原因なのと、原因調査の手順として「上流から順番に調べろ」というのがセオリーなのだろう。
そして次に多くヒットするのが、水栓と洗濯機を結ぶホースとか、接続部に詰まったゴミのトラブル。
これもおそらく水栓とホースが正しく接続されていない(最近の「洗濯機とか食洗機専用水栓」は漏水防止のため「止水弁」が付いているものもある。確実に接続されていないと水が流れない)というトラブルも多いのか。
そして井戸水などの自然水をそのまま使っている場合に「あるある」なのがゴミの付着。
地域差などもあるとは思うが、水道水ではなくミネラルを多く含む自然水は、それらの成分が付着(結晶化・固形化)する可能性がある。配管の老朽化による錆なども流れてくる。
まぁそもそも、そのような水を洗濯機に利用すること自体、許容していないと思うので、これで壊れるのは「自己責任」。しかも洗濯機の給水部だけでなく、それ以外の箇所も壊す可能性がある。
そして見つかったのが、洗濯機本体「給水弁部品」の故障
まぁ、厳密に言うと、この時点では「その可能性」というあくまで予測でしかない。つまり、それ以外の部品が故障している可能性もあるかもしれない。
もしも別の部品故障の場合、今回故障した我が家の洗濯機の場合、製造されてから15年以上経過しているため、もはや修理できない可能性が高い。
でも洗濯機本体の給水まわりの部品の中では、おそらくこの部品が機械的に最も動作を繰り返しているため、この部品が故障している可能性が高いと判断した。
自分で修理するか、メーカー修理(出張修理)してもらうか
我が家の製品は、某パ○ソニックの製品なので、いわゆる町の「パ○ソニックの店」に修理依頼という選択肢もある。
しかしながらこの「パ○ソニックの店」というのが、最近はちょっと信用できない。
というのも、彼らに修理を頼んだとしても「部品が製造終了でない」と言われる可能性があるのだが、それが「本当にないのか」が疑わしい。
ましてや出張修理の場合、その「出張料」すら請求される可能性がある。
そこで今回ネットで調べてみたところ、どうも部品自体は通販で単体入手できるうえ、しかも DIY で直せるような動画や Web のブログも見つけてしまった。
という事で自分で部品を取り寄せ、修理することに決定。
洗濯機の給水弁部品
ちなみにこの「給水弁部品」、部品としては 3,000 円前後のもので、送料も入れるとおそらく 4,000 円前後で入手できる。
ただし機種によって部品の種類が決まっているため、洗濯機の機種番号を必ず確認し、それに対応する部品を必ず入手する必要がある。
そして洗濯機などの家電製品、メーカーによっては製造終了後も何年間かは部品を保有している。
今回の場合は製造終了後、かなり時間が経過していたが、幸いなことに部品在庫が存在したため、修理の見通しが立てられた。
しかしながら部品がみつからない場合、(メーカーが推奨していないかぎり)他の部品で代用することは、かなり難しい。
もしそのような場合は、あきらめて新しい洗濯機を買った方がいい。
あと最近は、海外メーカーや家電から撤退したメーカーも多数ある。これらについての修理は、保証期間内でもないかぎり、修理はかなり絶望的ではないかと思う。
なので、個人的には特に海外メーカー品を購入する場合は、家電店の長期保証を付ける等して対策するしかないかと思う。
ちなみにこれが最後の「賭け」の部分になるのだが、「この部品を交換するだけでは直らない」可能性だって、正直ありえる。その場合、この部品代を始めとするあらゆる労力が無駄となってしまう。
部品を取り寄せている間に、給水部が完全に故障
洗濯をしても、給水がいつまでも洗濯槽に溜まらず、とうとう途中でエラーを吐き出すようになってしまった。
つまり洗濯ができない。
結局、修理が終わるまでは、何度か近所のコインランドリーを利用することに。
洗濯機は修理するまでが大変
そして部品が届き、ようやく修理。
と、その前に、修理をするためには洗濯機を移動させなくてはならない。
実はこの作業が重労働。
- 給水栓(水道栓)を閉じる。
- ホース内に残っている水を抜くために洗濯機を空回し。
(最初の給水だけ動作させ、途中で主電源OFF) - 電源コンセントとアースを抜く。
- ホース内残っている水が吹き出したり、垂れたりするおそれがあるため、バケツとタオルを駆使しながら、身長に給水ホースを取り外し。
- 排水ホースも、床に水が漏れないように注意しながら取り外し。
- 洗濯機本体を移動(重労働)
これが一番大変だった
修理自体は簡単
パナソニックの製品は、制御ユニット(基板部分)や給水部分が、本体の上部公報のカバー内にまとまっており、それらはビスを数個外せば、カバーも簡単に外せて、問題となった部品にアプローチすることができる。
スマホ写真は文明の利器
これは自分は修理の際に必ずやっている事なのだが、どこのネジを外して、内部がどうなっているかを写真で沢山撮りながら進めている。
これを行えば、修理後に修理前の状態と同じ状態で部品が設置したか比較できるし、写真の順番を辿れば、修理後の復元方法もわかる。
周辺部品に注意
今回の「給水弁部品」は、あくまで「給水弁部品」しか含まれていなかった。つまり部品に付いていたキャップ類やゴムパッキンなどは一切付属してこないので、もし壊れた部品にこれらの小さな付属品がある場合は、必ず交換後の部品に移植すること。
結束バンドが必要だった
今回、部品に接続していたホースには、水漏れ防止のため「結束バンド」が巻かれていた。今回それを切断しないと部品交換できないため、ペンチで切断したうえで部品交換したのだが、交換後もそのホースに対して、結束バンドを忘れずに巻き直す必要がある。
ただ、この結束バンドは交換部品には含まれていないので、必ず別途準備する必要がある。
幸いなことに我が家には、結束バンドの在庫があったので、それを使ったが、結束バンド自体は、100円ショップやホームセンターでも販売しているので、適宜あらかじめ購入する必要があるかと。
修理後の復元も大変
手順としては修理前の逆手順ではあるのだが、とにかく洗濯機は重い。
最後に試運転して終了
- 水栓を開いたのち、水漏れしていない事を確認。
- 洗濯機を最速モードで空回し運転。水がちゃんと洗濯槽に溜まって運転している事を確認。
- 次に、実際に洗濯物を投入して、普通に洗濯運転。
- 最後に給水口から水漏れがないかを確認。
問題なければ、修理完了
余談
個人的には今回はDIYで対応できたので記事にしてみたが、ご家庭によっては自前で修理できない場合も多いと思う。
あと普段こういった修理の知識や経験(というか、いわゆる「機械いじり」)に慣れていない人も、安全面などの責任などを考えると、正直やめておいたほうがいいです。
そういった方々は、大人しく家電屋さんに修理相談するか、購入してからの年数をみて、新しい洗濯機を買ったほうが良いと思います。